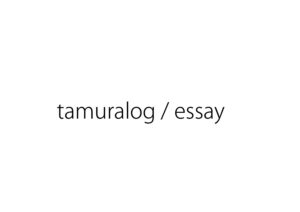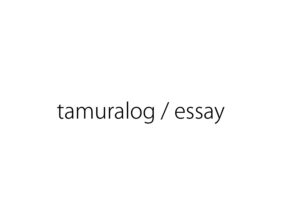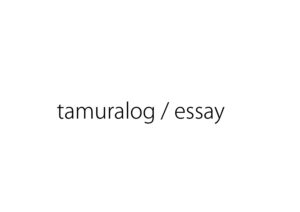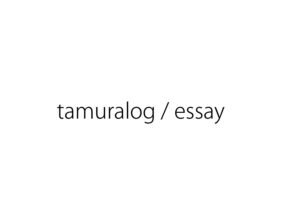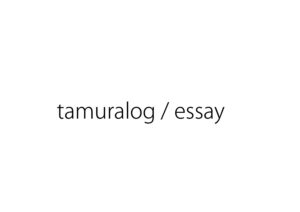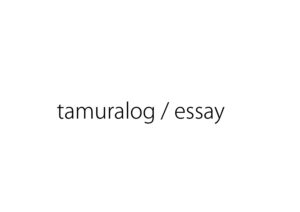スピルバーグによる映画『A.I.』が公開されたのは2001年でした。
もちろん「AI」というモチーフはずっと前から数々のSF作品に登場してきたことでしょう。
当時はまだまだ実用レベルではなく、未来の夢物語のように語られていたのかもしれませんが、今や私たちが日常的にお世話になるようなレベルにまで降りてきたテクノロジーになりました。
年始の新聞(※1)に、「AI近未来」と題してAIに関して特集が組まれていました。
昨年あたりから「チャットGPT」なんかがネット上を賑わしていましたが、一般レベルでは本格的な運用というよりもまだまだ面白がっているだけの段階なのかもしれません。
私の感覚ですが、世間で概ね耳にするのは、AIによって未来はバラ色というような側面だけでなく、そのマイナス面も心配するような印象で、それはそれでひじょうにいいことだなと思っています。
新聞の特集では、人手不足の過酷な現場などにAIを活用して人間のかわりに入っていけるだとか、医療技術というものをもっと日常的な場面で享受することを可能にするといったことについて取り上げられていました。
諸外国よりも高齢化社会への急速なシフトを余儀なくされている日本では、介護現場でのAI活用は喫緊の課題といえます。
記事で紹介されている技術で興味深かったのが医療現場における画像診断。
まだ臨床研究段階とはいえ、患者の動画撮影から糖尿病を約75%、高血圧を約90%の精度で的中させるといいます。
近い将来には病院に行かなくとも、鏡に内蔵させたAIカメラで毎朝、健康チェックができる未来がやってくるかも、という現場の声を紹介していました。
また創薬現場において、これまで膨大な時間と予算が必要だったものがAIによって大幅な短縮が見込まれます。
防犯対策においてもAIは、別の角度から新たな光を当ててくれるようです。
さまざまなデータを駆使した犯罪予測から、特殊詐欺の電話が入るとされたエリアを重点的に警戒したところ、被害を未然に防いだ事例もあったそうです。
このように書くと、AIがつくる未来は素晴らしい!と言いたくもなりますが、メリットだらけに見える世界をAIによってたぐりよせようとすることは、同じ深度で、同じ速度で、同じ距離で望ましくない世界にも近づいていくということを同時に意味することになります。
戦場では人がいなくなり無人の兵器同士の戦闘となり、外国への侵略の倫理的ハードルが低くなるのではないか。
実際にロシアや中国では街中に監視カメラがたくさん仕掛けられており、犯罪の抑止と引き換えに政治的弾圧にも利用されているという現実。
ワクチンの開発とは対照的に、新たなウイルスの合成を可能にするのかもしれない……。
犯罪抑止とはベクトルが逆の、詐欺にかかりやすい人たちのターゲティングへの応用。
2024年に「ディープラーニング」などの業績でノーベル物理学賞を受賞した「AI界のゴッドファーザー」とも呼ばれるジェフリー・ヒントン氏は次のようにいいます(※1)。
「開発企業が保有するコンピューターの処理能力を、AIの安全性の研究開発のために投じるよう義務づける法整備が要る。現在、AI開発企業が安全性の研究に使っている処理能力はおそらく1%程度。これを30%程度にひきあげるべきだ」
アメリカ次期大統領のトランプ氏の側近にイーロン・マスク氏がいますが、ヒントン氏はマスク氏がAI開発について安全規制を撤廃するようトランプ氏に助言する危惧があるとしています。
ジェフリー・ヒントン氏は約10年勤めたグーグルをAIの危険性を広く周知するために退社したとされ、私たちはその警鐘に真摯に耳を傾ける必要があります。
また、批評家・哲学者の東浩紀氏はこう言います(※1)。
「人間は非常に厄介で、正しい回答が示されても従うとは限らないし、双方にとって利益があると言っても問題が収まるとは限らない。現実の世界で人間同士の問題を解決するには、誰かが出て行く必要があり、その意味では政治家の役割は消えないし、外交も人間から引き離すのは難しいのではないか」
AIの知能が人間を上回ることに対する危惧から、ASI(=Artificial Superintelligence:人工超知能)による人類支配なんかもバッド・エンドとして想像してしまいがちです。
未来からターミネーターはやってきていませんので、いまのところ心配はないのかもしれませんが……。
冗談はさておき、たとえば核ミサイルの発射の判断をAIに任せるというのはSFだけの世界にしておいて、最後の安全弁は人間という存在に担わせないといけません。
交通事故が増えているから車を廃止する、スマートフォンを使った犯罪が増えているからスマートフォンを使用禁止にする、なんてことはもはや荒唐無稽な話として受け止めるしかないほど、それらはインフラとして私たちの生活に深く組み込まれてしまっています。
AIもすでに私たちの生活に深く根をはりめぐらせています。
ですから、私たちは同じようにAIの「使い方」を慎重に選んでいくしかありません。
ここまで考えてくると、ふと、自身が属する業界の未来について考えてみたくなります。
AIの登場によって、手工業や工芸といったジャンルは今後どうなって行くのでしょうか?
「製造業やサービス業では比較的影響が小さい一方、金融業や法律などの職種が影響を受けやすい」(※1)との調査もあるようですが、影響が小さいとはいえ変革の波は迫ってきます。
一般的に、業界として人材不足や不人気であったりするのは賃金と労働環境が見合ってなかったりするのが常ですが、例に漏れず、バッグや財布といったモノの製造現場はこれに該当するところが多いでしょう。
生活必需品というわけではありませんので、残念ながら市場の縮小は続いて行くのだと思います。
医療や介護の現場は同様に人材不足が叫ばれていますが、生活においてエッセンシャルな部分を担っていますので、優先的にAI化の取り組みが進んでいくでしょう。
では、私たちの業界は縮小してどうなっていくのかと言いますと、二極化とまでは言わないまでも、かなり偏った分布になるのではないかと思っています。
現在でも十分そうですが、ある種の製品はラグジュアリーな嗜好品としての意味合いをどんどん強めていく一方で、従来の製品づくりでは立ち行かなくなった現場はどんどん縮小・淘汰されて行くのでしょう。
とはいえ、ラグジュアリー以外をカバーしてくれる存在がないと困ります。
では、それはどんなものかというと、天然素材由来ではなく、合成素材による製造業の確立だと思うのです。
もちろん現段階でも、合成素材によるものづくりはたくさん行われています。
でもそれは従来の天然素材を相手にしてきた技術に、そのまま合成素材を代入してきただけのことで、いずれはその技術力がなくても成立するような製造現場が確立されていくと思います。
たとえば3Dプリンターの登場・発展などその最たるものでしょう。
合成素材もさまざまなものが、エシカルという名の大義名分のもと開発されていくに違いありません。
職人的技が発揮され、その技術力を支えられることが可能な現場(ラグジュアリー)だけが存続を許され、それ以外は過度にAI化の技術を流用した現場に取って代わられて行く……。
この技術はかばん作りに応用できる!というその発想転換の視点を多く持つことができる人がこれからは活躍していくのかもしれません。
思想家・武道家の内田樹氏は、『身体知性』(※2)の中で著者・佐藤友亮氏との対談において、AIの限界を「スキャン」と「エディット」という二つの観点から論じています。
AIは過去の何らかのデータをフラットに並べて超高速にスキャンすることは得意だろうけど、記憶をアーカイブすることはできないとします。
曰く、「記憶というものは実体がな」く、「新しい経験をするたびに僕たちの記憶は全部書き換えられます」。
つまり、ある人にとっては何らかの経験が過去の出来事を想起させ、自身の記憶があらたにその都度生成・書き換えらて行くという経過を辿ることになります。
すべてをフラットに扱うのではなく、今まで忘れていた過去の記憶を突然思い出すといった、どの記憶に「重し」をつけるのかは、その人独自のエディットによるものです。
興味深い例としてアナグラムが挙げられていました。
ある単語が多くの人にとってはそのままに受け止められるのに、ある人にはドキッとするものとして認知されてしまう。
勝手に頭の中で、アナグラム的に別の単語を想起してしまっているのです。
内田氏はそれをある種の「頭の悪さ」というように表現しています。
こう書くと、処理能力の低さと誤解してしまいそうですが、もう少し言葉の意味をゆるめて考えると、その人なりの「認知のくせ」というべきものをそれぞれが持っていて、結果としてそれが個々人の認知の歪み(≒個性)を生じさせる、ということになるんだと思います。
これらを踏まえますと、過去の膨大なコレクションをフラットにスキャンし、データとしてビルトインしたとしても、そこから生み出されたそのあまりにも優秀なアウトプットには奥行き(人間の認知の歪みというフィルターを通したオリジナルなコンテクスト)が感じられず、面白みにかけてしまう、、、のかもしれません。
つまり、その部分において、まだまだ人間には活躍の場があるんじゃないでしょうか。
ーーーーー
※1 読売新聞2025年1月3日〜7日(いずれも朝刊)「AI近未来」を参照
※2 佐藤友亮『身体知性』 朝日新聞出版 2017